|
こだわりの刀

こだわりの刀などを使って作業する筆者 |
「装芸画」の一番の特徴は、世界中のどんな裂(きれ)でも、しかも新旧を問わず、何でも裏打ちして、絵の具と見立てて使われていることです。ただ、どうしても私がアピールしたくなるのは、表面に表れない影の引き立て役たちなのです。すでに、このコラムでは、最初に、原木によって、異なる性格を秘めた手漉き和紙のこと、次には頼りがいのある力強い「打ち刷毛」のことに触れてきました、今回は、もうひとつ、なくてはならない“切れ者”の「刀」(とう)の存在です。
わが師匠ながら、よくぞそこに目をつけた、と感心するのですが、もともと表具師の工房には、必ず何種類かの幅の異なる鑿(のみ)があるのです。その中には、屏風など、ふちの内側に表から釘が見えないように溝を彫るための二分(にぶ=約6㍉)の細い鑿があります。これを加工し、研ぎ上げることによって、どんなカットでも可能になった不思議な「こだわりの刀」が誕生したのです。
よく、道具は、手や指の延長であると言われますが、中でも「刀」は、装芸画の要といえるでしょうか。修行を重ねて、手指の如く使いこなして、美しい画面を創り出していきたいものです。
めまぐるしく遷移するファッション業界などに比べると、対称的に、鎌倉時代から形式や寸法、仕立ての方法など、むしろ、変えることなく受け継がれているのが表装です。が、あくまでも書画を引き立てて保存するための脇役といえるでしょう。
それはそれで、大切な役目かとは思いますが、前にも触れましたように、現代人の生活様式から離れている中で、同じ素材、技法を使いながら主役でありうる装芸画の存在は、これを紹介し、広めることにより、世界に誇れる奥深い日本の伝統工芸の再確認を喚起するものだと思うのです。
匠と名乗るのはおこがましいのですが、つぶやくことに意義を感じでいるこのごろの私です。
|
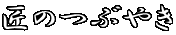 Vol.5
Vol.5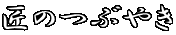 Vol.5
Vol.5